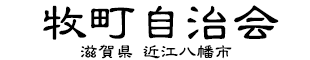子供松明づくり教室を開催

令和7年3月23日(日曜日)
”子供松明”は、五社神社 例大祭の宵宮祭で実施される祭事の一つで、子供の健やかな成長を願い、各ご家庭から奉納される全長80cm~120cmの松明で、例年5月3日15時からの子供神輿の後に奉火されます。
核家族化とコロナ過の影響で縮小傾向となってきている地元、五社神社の松明祭り(五社神社 宵宮祭・例大祭)を盛り上げていく取り組みの一つとして、牧町自治会、五社神社による「子供松明づくり教室」が開催されました。
当日は、午前中のみだったため、子供松明の胴体部分を作る作業で、御幣の取り付けや、飾りつけは各ご家庭で行っていただく事とし、菜種ガラを芯にしその周りをヨシで覆い、そのヨシを曲げ(折る)上部に傘を作る作業を実施しました。
まずは、ヨシの皮をむく所から作業開始です。1本の松明に約100本のヨシが必要で、この作業は大人でも結構根気が要り大変な作業です。最初は子供たちも一生懸命皮むき作業をおこなっていましたが、気が付くと作業をしているのは大人ばかり……。

次に、菜種ガラを束にし縄でしばりつけ、松明の胴体を作ります。(下写真の赤矢印)

次に、皮むき作業を終えたヨシの穂先をそろえ、約1m60cm程度の長さに切りそろえ、80cmほどに切り取ったガムテープに穂先をそろえ、1本づつ貼り付け(仮止め)ていきます。

ガムテープに仮止めしヨシがシート状になった上に松明の胴体となる菜種ガラを乗せ、ヨシのシートを菜種ガラに巻き付け、ヨシが均一になるよう注意しながら縄でしばりつけます。
※ ここでヨシをしばりつけている縄の結び方(男結び)が重要になりますが、男結びができる大人が少なくなってきているのが大きな課題です。
また、この結び目に松明の持ち手となる竹を結ぶため、結び目の位置を合わせる必要があります。
この状態で、一番上の縄部でヨシを折り曲げ、松明の「傘」を作りますが、乾燥したヨシは折れやすいため、折り曲げようとする部分を充分に水で濡らし柔らかくし、外に広げるよう折り曲げていきます。
ヨシを外に折り曲げた所に竹で作った輪っかをはめ込み、傘の広がり具合を調整しながら、細いひもでしばり付け、松明の本体部分が仕上がります。(下写真)

今回は、初めての取り組みでもあり、サポートするスタッフの知識不足もあり時間を要してしまいましたが、このような取り組みを今後も続けていく事で、牧町に伝わる伝統の松明づくりを継承していく事につながっていくのだなと実感したしだいです。